退職時の情報持ち出し注意点
退職を決意した瞬間から、多くの方が直面する重要な問題が「会社の情報をどこまで持ち出せるのか」という点です。長年働いた会社では、自分が作成した資料やノウハウ、顧客リストなど、様々な情報に触れる機会があります。「自分が作ったものだから」「次の仕事に役立てたい」という気持ちは理解できますが、法的リスクを伴う行為であることを認識しておく必要があります。
情報持ち出しの法的リスク
情報持ち出しに関する法的リスクは想像以上に大きいものです。経済産業省の調査によれば、退職者による情報持ち出しのトラブルは年間数百件報告されており、訴訟に発展するケースも少なくありません。具体的には以下のリスクがあります:

– 不正競争防止法違反: 営業秘密の不正取得・使用は、最大10年の懲役または2000万円以下の罰金
– 著作権法違反: 会社が著作権を持つ資料の無断持ち出しは著作権侵害
– 民事上の損害賠償: 会社に損害を与えた場合、数百万〜数千万円の賠償責任が生じる可能性
– 秘密保持契約違反: 入社時や退職時に締結した契約に基づく責任追及
持ち出し禁止の対象となる情報
特に注意すべき情報には次のようなものがあります:
– 顧客リストや取引先情報
– 製品の設計図や仕様書
– 社内マニュアルや業務フロー
– 経営戦略や営業戦略に関する資料
– 研究開発データや実験結果
– 社内システムのアクセス情報やパスワード
東京地裁の判例では、「自分が作成した資料であっても、業務上作成したものは会社に帰属する」という判断が示されています。「これくらいなら大丈夫」という安易な考えが、後に大きなトラブルを招く原因となりかねません。
情報持ち出しの問題は、単なる法的リスクだけでなく、キャリアにも深刻な影響を与える可能性があります。次のセクションでは、具体的にどのような行為が問題となるのか、そして適切な対処法について詳しく見ていきましょう。
退職時の情報持ち出しに関する法的リスクと秘密保持義務
退職を考える際、多くの方が気になるのが「会社の情報をどこまで持ち出せるのか」という問題です。特に次のキャリアに活かしたいと考えるのは自然なことですが、法的リスクを正しく理解しておかなければ、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
秘密保持義務の法的根拠
秘密保持義務は主に以下の法律に基づいています:

– 不正競争防止法:営業秘密の不正取得・使用・開示を禁止
– 労働契約法:労働者の誠実義務として秘密保持が含まれる
– 刑法:業務上知り得た秘密を漏洩した場合の罰則規定
2019年の経済産業省の調査によると、営業秘密侵害事件の約40%が退職者による情報持ち出しに関連しています。特に技術情報や顧客データの持ち出しが多く、訴訟に発展するケースも少なくありません。
持ち出し禁止情報の具体例
以下の情報は原則として持ち出し禁止とされています:
– 顧客リストや連絡先情報
– 製品の設計図や製造方法
– 未公開の事業計画や戦略資料
– 社内システムのID・パスワード
– 価格設定や取引条件に関する情報
特に注意すべきは、「自分が作成した資料だから」という誤解です。会社の業務として作成した成果物の著作権は原則として会社に帰属します。東京地裁の2018年の判決では、自身が作成した営業資料を持ち出した元社員に対し、約500万円の損害賠償が命じられた事例があります。
情報持ち出しのグレーゾーン
一方で、以下のような情報は判断が難しいケースがあります:
– 業務上習得したノウハウや経験
– 公開情報から作成した業界分析
– 自分の業績記録や評価情報
これらについては、会社との秘密保持契約の内容や、情報の性質、持ち出し方法によって判断が分かれます。特に注意が必要なのは、在職中に次の就職先のために意図的に情報を収集する行為です。これは「背任行為」として法的責任を問われる可能性が高くなります。
持ち出し禁止情報と持ち出し可能情報の明確な線引き
会社の情報には「絶対に持ち出してはいけないもの」と「条件付きで持ち出し可能なもの」があります。この境界線を明確に理解することは、退職時のトラブル回避において極めて重要です。特に近年は、不正競争防止法の改正や個人情報保護法の厳格化により、情報の取り扱いに対する法的責任が強化されています。
持ち出し禁止情報の具体例

以下の情報は、原則として持ち出しが禁止されています:
– 顧客情報:連絡先、購買履歴、契約内容など
– 営業秘密:製品開発情報、製造方法、原価情報
– 経営戦略資料:事業計画書、M&A関連情報
– 未公開の財務情報:内部の売上予測、収益構造
– 人事情報:給与データ、人事評価情報
– 社内システムのアクセス情報:ID、パスワード
経済産業省の調査によると、営業秘密の漏洩事件の約7割が退職者によるものとされています。違反した場合、民事上の損害賠償請求だけでなく、不正競争防止法違反で最大10年の懲役または2000万円以下の罰金(またはその両方)という刑事罰の対象となる可能性があります。
持ち出し可能な情報の判断基準
一方、以下の情報は一般的に持ち出しが許容される可能性があります:
– 自分自身が作成した業務成果物(ただし、会社の著作物と認められる場合は要注意)
– 自分のスキルとして身についた知識やノウハウ(頭の中に入っている情報)
– 公開情報から作成した資料(誰でもアクセス可能な情報を基にしたもの)
– 自分の給与明細や雇用契約書のコピー(自己の権利に関わるもの)
判例では、「業務上知り得た情報」と「業務経験から得た知識・技能」は区別されており、後者は原則として持ち出し可能とされています。ただし、この線引きは非常に微妙で、東京地裁平成29年9月の判決では、「顧客情報を記憶して持ち出す行為」も不正競争に当たると判断されたケースもあります。
重要なのは、「その情報が会社固有のものか」「一般的な知識・スキルか」という点です。不明確な場合は、必ず会社の情報セキュリティポリシーを確認するか、法律の専門家に相談することをお勧めします。
情報持ち出しを検討する前に確認すべき社内規定と契約内容
退職を考える際、自分の業務に関連する情報や資料を持ち出したいと考えることがあるかもしれません。しかし、これは法的・倫理的に大きなリスクを伴う行為です。まずは自社の規定や契約内容を正確に理解することが不可欠です。
就業規則と情報セキュリティポリシーの確認
多くの企業では、情報の取り扱いについて就業規則や情報セキュリティポリシーで明確に規定しています。2022年の調査によると、日本企業の87%が情報持ち出しに関する明確な社内規定を設けているとされています。退職前に必ず確認すべき項目には以下があります:

– 社内文書の社外持ち出し禁止条項
– 電子データの外部デバイスへの保存・転送に関する規定
– 退職時の情報返却・破棄義務
– クラウドサービス利用に関するポリシー
これらの規定に違反した場合、懲戒処分や損害賠償請求の対象となる可能性があります。
秘密保持契約(NDA)の再確認
入社時や特定のプロジェクト参加時に締結した秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement)の内容を再確認しましょう。特に注意すべき点は:
– 秘密情報の定義範囲(顧客情報、営業情報、技術情報など)
– 守秘義務の期間(退職後も継続する場合が多い)
– 違反時の罰則規定
実際のケースでは、大手IT企業の元社員が自作の業務効率化ツールのソースコードを持ち出し、新しい職場で使用したことで前職から訴えられ、約800万円の損害賠償を命じられた事例があります。
競業避止義務の確認
特に専門職や管理職の場合、競業避止義務が契約に含まれていることがあります。これは退職後一定期間、同業他社での就業や類似事業の起業を制限するものです。情報持ち出しと組み合わさると、法的リスクが著しく高まります。
東京地裁の判例では「競業避止義務の有効期間は通常6ヶ月〜2年程度」とされていますが、職種や保護すべき企業秘密の性質によって異なります。不明点がある場合は、弁護士など専門家への相談を検討しましょう。
自分の業務成果と企業秘密を適切に区別する方法
自分の業務成果と企業秘密を区別することは、退職時のトラブル回避において極めて重要です。多くの方が「自分が作ったものだから」という認識で情報を持ち出してしまい、後にトラブルとなるケースが少なくありません。法的リスクを避けながら、自分の実績やスキルを適切に次のキャリアに活かす方法を解説します。
業務成果と企業秘密の境界線
業務中に培った「スキル・知識・経験」と「企業固有の秘密情報」は明確に区別する必要があります。前者は退職後も活用できますが、後者は持ち出し禁止です。以下の判断基準を参考にしてください:

– 持ち出し可能なもの:
– 一般的な業務知識・スキル
– 公開情報から作成したデータ分析手法
– 自分自身の職務経歴(実績の事実)
– 持ち出し禁止なもの:
– 顧客情報・リスト
– 社内マニュアル・業務フロー
– 未公開の製品情報・企画書
– 取引先との契約内容
東京地裁の判例では、「業務上知り得た情報であっても、一般的スキルとして習得した知識は競業避止義務の対象外」とされています。しかし、具体的な企業固有データは明確に保護対象です。
ポートフォリオ作成の正しい方法
転職活動でポートフォリオが必要な場合、以下の方法で法的リスクを回避できます:
1. 匿名化処理:顧客名や固有情報を完全に削除・加工する
2. 概念化:具体的数値ではなく、成果の「割合」や「概要」で表現する
3. 事前許可:上司や法務部門に確認し、書面での許可を得る
4. 一般化:「A社向けWebサイト制作」→「小売業向けECサイト構築」など
実際に、デザイナーやエンジニアの約65%が「業務成果を適切に加工してポートフォリオ化している」というアンケート結果があります(2022年・キャリア支援協会調査)。
グレーゾーンを避けるための実践的アプローチ
判断に迷う場合は、以下の3つの質問で自己チェックしてください:
1. その情報は一般に公開されているか?
2. その情報がなくても次の職場で業務遂行できるか?
3. 元の会社が情報持ち出しを知ったら訴訟リスクがあるか?
一つでも不安がある場合は持ち出さないことが賢明です。秘密保持義務違反による訴訟では、平均して300〜500万円の損害賠償請求が行われるケースもあります。
退職時には、自分のキャリア資産を守りながらも法律を遵守することが、次のステージでの成功につながります。自分の知識とスキルは持ち出せますが、企業固有の情報は必ず会社に残すという原則を守りましょう。
ピックアップ記事
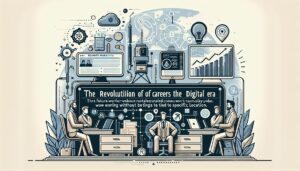




コメント