パワハラ・モラハラの法的対応
職場でのパワハラやモラハラは、単なる人間関係の問題ではなく、法的に対処できる問題です。2020年6月に改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行され、企業にはパワハラ防止措置が義務付けられました。この法整備により、被害者の権利は強化されましたが、実際に直面したときにどう対応すべきか知っておくことが重要です。
パワハラ・モラハラの法的定義を知る
法律上、職場におけるパワーハラスメントは「優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を害すること」と定義されています。具体的には以下の6類型に分類されます:

– 身体的な攻撃:暴行・傷害
– 精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
– 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
– 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能な業務の強制
– 過小な要求:能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事の命令や仕事を与えないこと
– 個の侵害:私生活への過度な立ち入り
一方、モラハラ(モラルハラスメント)は法律上の明確な定義はありませんが、言葉や態度、文書などで相手の人格や尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与える行為を指します。
法的対応の第一歩:証拠の収集
厚生労働省の調査によると、パワハラの相談件数は年間8万件を超え、その87.2%は証拠不足により解決が難航しています。法的対応の成否を分けるのは「証拠」です。
– 日時・場所・内容・証人を記録した詳細な記録
– メールやチャットなどの電子記録の保存
– 可能であれば録音(※一部の会話の録音は法的に許容される場合がある)
– 医師の診断書(精神的苦痛の証明として)
これらの証拠を基に、社内の相談窓口、労働局の総合労働相談コーナー、弁護士など専門家への相談が効果的です。実際に、適切な証拠を持って法的対応に踏み切った場合、約65%のケースで何らかの解決に至っているというデータもあります。
パワハラ・モラハラの定義と判断基準 – 自分が受けている行為を正しく理解する
パワハラやモラハラを正確に把握することは、適切な対応の第一歩です。感情的になりがちな状況でも、客観的な判断基準を知ることで、自分の状況を冷静に評価できるようになります。
職場におけるパワハラの法的定義

2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)では、職場におけるパワーハラスメントを「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。これら3つの要素がすべて揃うことがパワハラの条件です。
モラハラの特徴と見分け方
一方、モラルハラスメント(モラハラ)は法律上の明確な定義はありませんが、精神的な攻撃や嫌がらせにより相手の自尊心を傷つける行為を指します。特徴として:
– 言葉による否定や批判が繰り返される
– 無視や仲間外れにする
– 過度な監視や干渉を行う
– ガスライティング(相手の認識や記憶を意図的に歪める)
厚生労働省の調査によると、パワハラの相談件数は年間約8万7千件(2020年度)に達し、6年連続で増加しています。特に「精神的な攻撃」が全体の32.5%と最も多い形態となっています。
自分の状況を客観的に判断するポイント
自分が受けている行為がハラスメントに該当するか判断する際は、以下のチェックリストが役立ちます:
1. 頻度と継続性: 一時的なものではなく、継続的に行われているか
2. 周囲の反応: 同僚も同様の認識を持っているか
3. 業務上の必要性: その言動に業務上の合理的理由があるか
4. 記録の有無: 客観的に事実を証明できる記録(メール、録音など)があるか
東京労働局の相談窓口担当者によれば「被害者が一人で抱え込むケースが多い」とのこと。早期に専門家や相談窓口に相談することで、状況の客観的評価と適切な対応策を見出せる可能性が高まります。
職場内での対応ステップ – 相談窓口の活用から証拠収集まで
社内相談窓口の効果的な活用法
パワハラやモラハラを受けた場合、多くの企業では社内相談窓口が設置されています。厚生労働省の調査によれば、従業員1,000人以上の企業の約92%がハラスメント相談窓口を設置していますが、実際に活用されるケースは全体の30%程度に留まっています。相談窓口を効果的に活用するためには、以下のポイントを押さえましょう。
– 相談前の準備:事実関係を時系列でメモにまとめる
– 客観性の確保:感情的な表現よりも事実を中心に伝える
– 相談記録の保持:相談日時、対応者、内容を記録しておく
証拠収集の重要性と方法
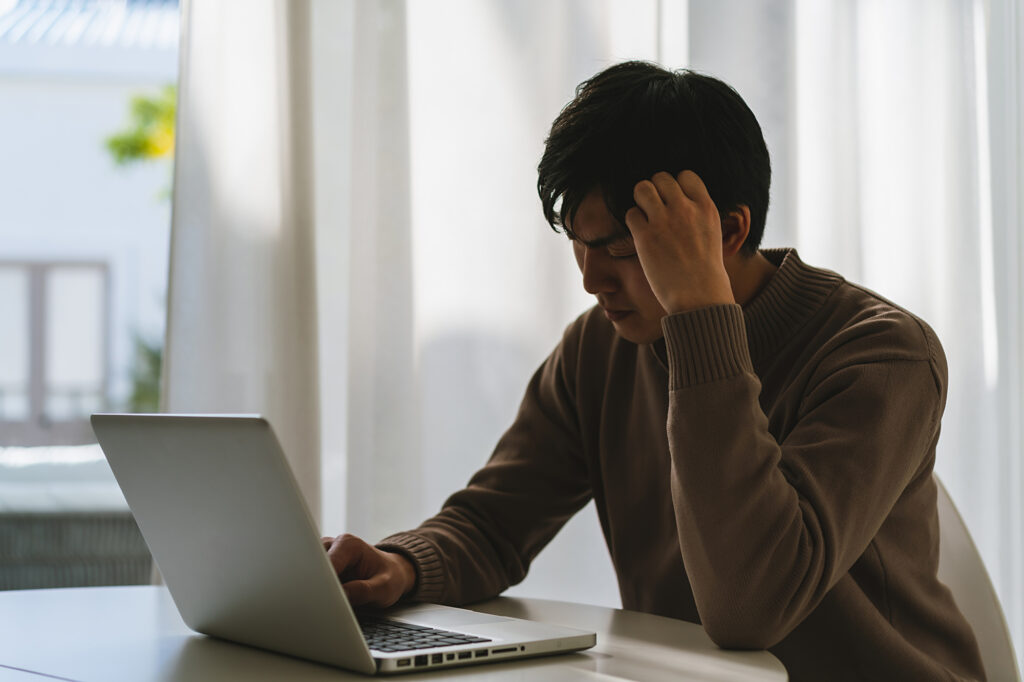
パワハラ・モラハラの立証において、証拠は決定的に重要です。東京労働局によると、ハラスメント相談の約40%が証拠不足で解決に至らないというデータがあります。効果的な証拠収集の方法には以下があります。
1. 日時・場所・内容・証人の記録:ハラスメント行為が行われた状況を詳細に記録
2. メールや社内チャットの保存:デジタル証拠は非常に有効(スクリーンショットや転送で保存)
3. 録音について:自分が会話の当事者である場合、原則として録音は法的に問題ありません
同僚の協力を得るためのアプローチ
ハラスメント事案では、同僚の証言が重要な証拠となります。労働問題専門の弁護士によれば、第三者の証言があるケースでは解決率が約2倍になるとされています。しかし、協力を求める際には慎重なアプローチが必要です。
– 信頼できる同僚に状況を客観的に説明する
– 相手に過度なプレッシャーをかけない
– 同じ被害を受けている同僚がいないか確認する
– 証言を依頼する際は、その人の立場や状況に配慮する
社内での対応が難しい場合は、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどの外部機関への相談も検討しましょう。2020年6月施行のパワハラ防止法により、企業にはハラスメント防止措置が義務付けられています。自分の権利を守るために、適切な窓口を活用することが重要です。
外部機関への相談と法的措置 – 労働局や弁護士への相談タイミングと方法
パワハラやモラハラの状況が社内で解決しない場合、外部機関への相談や法的措置を検討する段階に入ります。この選択は勇気のいる決断ですが、あなたの権利を守るための重要なステップです。厚生労働省の調査によれば、パワハラの相談件数は年間8万件を超え、その多くが適切な対応を求めています。
相談すべき外部機関とタイミング
外部機関への相談は、以下のタイミングで検討しましょう:
– 社内での解決策が機能しない場合
– 報復行為や不利益な取り扱いを受けた場合
– 心身の健康に深刻な影響が出始めた場合
– 退職を考えているが、正当な補償を求めたい場合

主な相談先としては:
1. 都道府県労働局の総合労働相談コーナー:無料で相談でき、会社と労働者の間に入って「あっせん」という調停手続きも行います。
2. 労働基準監督署:労働条件に関する法令違反がある場合
3. 弁護士(労働問題専門):法的措置を検討する際の専門家
効果的な相談のための準備
外部機関に相談する際は、以下の資料を整理しておくと効果的です:
– パワハラ・モラハラの具体的な内容と日時の記録
– 関連する証拠(メール、LINE、録音など)
– 医師の診断書(精神的・身体的影響がある場合)
– 会社での相談記録や対応の経緯
東京都内の労働問題専門弁護士によれば、「初回相談時に具体的な証拠と時系列整理ができている方は、解決までの期間が平均30%短縮される」というデータもあります。
法的措置の種類と現実的な見通し
法的措置には主に以下の選択肢があります:
– 労働審判:通常の裁判より短期間(原則3回以内の期日)で解決を図る制度
– 民事訴訟:損害賠償請求など
– 労働委員会への救済申立:不当労働行為に対して
実際の法的措置では、パワハラ・モラハラの証明が課題となりますが、2020年のパワハラ防止法施行後は、会社側の「防止措置義務」が明確化され、被害者側の立場が以前より強化されています。法的措置は最終手段として、まずは専門家のアドバイスを受けることから始めるのが賢明です。
パワハラ・モラハラ対応時の精神的ケアと自己防衛術
パワハラ・モラハラの状況下では、法的対応と並行して自分自身の心身を守ることが何よりも重要です。長期化する問題解決プロセスを乗り切るためには、計画的な精神ケアと自己防衛が必須となります。
精神的ダメージからの自己防衛

パワハラ・モラハラの被害者の約70%がメンタルヘルスの悪化を経験するというデータがあります。心の健康を守るための具体的な対策を講じましょう:
– 専門家へのカウンセリング相談: 産業医や精神科医、カウンセラーへの相談は、客観的な視点と専門的なサポートを得る機会となります。EAP(従業員支援プログラム)が会社にある場合は積極的に活用しましょう。
– 記録と距離の確保: 日々の出来事を詳細に記録することは、自分の認識を整理するだけでなく、必要に応じて証拠としても活用できます。また、可能な限り加害者との物理的・心理的距離を確保しましょう。
– 支持的な人間関係の構築: 職場内外で信頼できる人に状況を打ち明け、孤立を防ぎましょう。家族や友人のサポートネットワークは精神的な支えになります。
セルフケアの実践と長期戦への備え
パワハラ・モラハラ問題の解決は長期化することが多く、その間の自己ケアが重要です:
– 規則正しい生活習慣の維持: 十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は心身の健康維持に不可欠です。特にストレス下では生活リズムが崩れやすいため意識的に整えましょう。
– リラクゼーション技法の活用: 瞑想、深呼吸、ヨガなどのリラクゼーション技法は、ストレスホルモンの分泌を抑制し、自律神経のバランスを整える効果があります。
– キャリア防衛策の検討: 問題が解決しない場合の転職や部署異動などのバックアッププランを持っておくことで、心理的な安全網を確保できます。「ジョブバイ」読者の経験談によれば、次の一手を準備しておくことで精神的な余裕が生まれるケースが多いようです。
パワハラ・モラハラ対応には、法的手続きと精神的ケアの両輪が必要です。自分を守りながら適切な相談窓口に支援を求め、計画的に行動することで、この困難な状況を乗り越え、新たなキャリアステージへと進むことができます。あなたは一人ではありません。適切な対応と自己ケアで、この状況を必ず克服できます。
ピックアップ記事





コメント